
カーポートを作るときに確認申請は必要?

しなかったらどうなるの?

確認申請は、自分でできるの?
そんな疑問に答えます。
確認申請とは、違法な建築物を建てないように、工事する前に、審査機関による設計内容の審査を受ける制度です。
- カーポートの確認申請が必要なケース・不要なケースを解説します。
- カーポートが守らないといけない建築基準法の規定を紹介します。
- 自分で確認申請するのが難しい理由も分かります。

私は、一級建築士の資格を持っており、建築関係の会社で5年以上働いています。
そのため、建築の専門知識や業界事情に詳しいです。
そんな私が、カーポートの確認申請や、建築基準法の規定について解説します。
カーポートを作る場合は、確認申請をしないと違法になってしまうケースが多いです。
確認申請をしなかった場合、近隣住民からの通報で行政指導を受けたり、将来家の増築が困難になったりする可能性があります。
この記事を読めば、カーポートに関する建築基準法・確認申請のルールが一通り理解できます。
一級建築士である私がわかりやすく解説するので、ぜひ最後まで読んでみてください。
カーポートの設置は、外構工事に分類されることが多いです。カーポートを作りたいと考えている方は、一括見積サイトの利用がおすすめです。
一括見積サイトを利用することで、簡単に複数の業者から見積もりを取り寄せ、適正な価格を知ることができます。
こちらの記事で、有名な外構工事一括見積サイト6社を比較しています。
カーポート設置には、1台分でも確認申請が必要

都市計画区域内・準都市計画区域内にカーポートを設置する際は、建築基準法に基づき確認申請をする必要があります。
まずは、カーポート設置を依頼する外構業者・ホームセンターやハウスメーカーに、確認申請の対応もしてくれるのか確認しましょう。
これらの業者が引き受けてくれない場合は、お近くの建築士事務所に依頼しましょう。
カーポートは建築物に該当する場合がほとんど
屋根のあるカーポートは、建築物に該当します。 建築基準法第2条に書いてある通り、屋根と柱がある工作物は建築物に該当するためです。
建築物に該当する場合は建築基準法が適用されるため、屋根のあるカーポートは建築基準法を守らないといけません。
屋根を設置しない、ただの青空駐車場は建築物に該当しないため、建築基準法は適用されません。
建築基準法
(用語の定義)
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。引用元:e-GOV法令検索

ちなみに、建築基準法第2条の中で「土地に定着する」という言葉がありますが、カーポートはほとんどの場合、土地に定着しています。
土地に定着していないケースとは、「いつでも自由に移動させることができる」状態を指しているからです。
土地に定着していない(建築物に該当しない)ケースの例
- 一時的に置いているコンテナ
- 公道を走ることができるトレーラーハウス
確認申請が必要なケース
カーポートを新設するとき、確認申請が必要となるケースは次の通りです。
よほどの田舎(都市計画区域外・準都市計画区域外)に建てる場合を除いて、カーポートを新設するときは確認申請が必要となります。
- 敷地が都市計画区域内・準都市計画区域内 で、新設するカーポートの面積が10m2超の場合
- 防火地域、準防火地域内の敷地に建てる場合(面積が10m2以内でも必要)
- 都市計画区域内・準都市計画区域内で、家とは別の敷地に建てる場合(面積が10m2以内でも必要)
(敷地が都市計画区域内にあるかどうかは、市区町村のホームページを見るか、市区町村に問い合わせることで確認できます。ざっくり言えば、よほど田舎でない限り、都市計画区域内であるケースが多いです。ちなみに都市計画区域と市街化調整区域が混同されやすいですが、全くの別物です。)

カーポートは1台分の場合でも3m×6m=18m2くらいの面積となるため、屋根のあるカーポートを新設するときは、まず間違いなく確認申請が必要です。
確認申請が不要なケース
屋根のあるカーポートを新設する際でも確認申請が要らないケースは、次の通りです。
- 都市計画区域外・準都市計画区域外に建てる場合(面積が200m2以内の平屋に限り不要)
- 防火地域外・準防火地域外の敷地に 10m2以内のカーポートを増築する場合
建築基準法
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条
建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
二 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物
三 前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。引用元:e-GOV法令検索
カーポートにかかる建築基準法の規制内容

カーポートを新設するとき守らないといけない建築基準法の規制で、代表的なものは次の通りです。
- 構造関係規定
- 屋根の防火性能の規定
- 集団規定
構造関係規定
建築物は、以下のような荷重がかかっても壊れないように作る必要があります。
これらの荷重がかかっても建物が壊れないようにするための規定を構造関係規定といいます。
- 固定荷重や積載荷重(カーポートの自重など)
- 地震力
- 風荷重
- 積雪荷重
カーポート自体は、メーカー(LIXILやYKKAPなど)が、構造関係規定に適合しているか検討したうえで、製品として販売している場合が多いです。
カーポートの基礎は、敷地の地耐力(地面の強さ)に応じて、構造関係規定に適合するものを選定する必要があります。
(主な構造関係規定は、建築基準法第20条と建築基準法施行令第3章の規定です。)
屋根の防火性能の規制
カーポートを建てる敷地が、
- 防火地域
- 準防火地域
- 法22条区域
の中にある場合、屋根の防火性能の規制がかかります。
具体的には、屋根を金属屋根(不燃材料)などにするか、DR認定やUR認定を受けた屋根にする必要があります。
建築基準法
(屋根)
第二十二条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。(屋根)
第六十二条 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。引用元:e-GOV法令検索
集団規定
都市計画区域内・準都市計画区域内でカーポートを設置する場合は、集団規定(建築基準法第3章の規定)を守らないといけません。
カーポートに影響する集団規定の代表的なものは、次の通りです。
- 2項道路(建築基準法第42条第2項)
→敷地の前面道路が2項道路の場合は、カーポートもセットバックが必要です。(原則、道路中心線から2m) - 用途地域(建築基準法第48条)
→第一種・第二種低層住宅専用地域などでは、住宅と別の敷地にカーポート単体を新設することはできません。 - 容積率(建築基準法第52条)
→敷地の広さに応じて、床面積(柱で囲まれた面積)の制限を受けます。カーポートのような開放的な建築物には緩和規定があります。 - 建ぺい率(建築基準法第53条)
→敷地の広さに応じて、 建築面積(建物の水平投影面積)の制限を受けます。壁がないカーポートの場合は緩和規定があります。 - 高さ制限(建築基準法第56条)
→専門的なので詳細は省きますが、カーポートがあることで道路からの後退距離が少なくなり、住宅本体に適用される高さ制限が厳しくなる場合があります。(建築基準法第56条第2項)
確認申請をしなかった場合は?あとからでもできる?

確認申請をしなかった場合
確認申請をせずにカーポートを建ててしまった場合、近所の住民等からの通報等によって、都道府県や市区町村から指導を受ける可能性があります。
確認申請をして審査に合格すると確認済証がもらえます。工事中は、確認済証の内容を看板にして立てておかないといけません。そのため「看板を立てていない」→「確認申請をしていない」という風に近所の人にバレてしまうんです。
また、確認申請をせずにカーポートを建てるということは、建築基準法の適合状況について第三者のチェックがされていない状態です。つまり違法なカーポートを建てている可能性があります。
将来、住宅の増築などをする際に、敷地内に違法なカーポートがあるせいで、確認申請を下せなくなってしまう危険があります。
また、確認申請をしなかった場合、罰則を受ける可能性もゼロではありません。
建築基準法第99条では、確認申請をしなかった場合の罰則規定として、1年以下の拘禁刑または100万円の罰金が定められています。
建築基準法
(工事現場における確認の表示等)
第八十九条 第六条第一項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。第七章 罰則
第九十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の六第一項(第八十七条の四又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十九第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者引用元:e-GOV法令検索
工事完了した後に確認申請はできない
確認申請は工事に着手する前にする決まりなので、工事が完了した後に確認申請をすることはできません。
工事中であれば、都道府県や市町村によっては、確認申請を受け付けてくれるかもしれません。
自分で確認申請する難易度は相当高い

カーポートの確認申請を自分でやる難易度は相当高いです。
難易度が高い理由は次のとおりです。
カーポートの確認申請を自分でやる難易度が高い理由
- 設計者が建築士でない場合、4号特例が適用されない。
- 書類作成や、審査機関とのやり取りに専門知識が必要 。
4号特例とは「小規模な建築物を”建築士が”設計した場合、確認申請で構造関係書類などを提出しなくて良い」という特例です。
建築士以外が設計者の場合は構造関係書類も審査されるので、確認申請を通す難易度が高くなります。
また、書類作成や審査機関とのやり取りにも、建築基準法などの専門知識が必要です。そのため、専門知識が無い一般人が確認申請をするのは難易度が高いです。
まずは、カーポート設置を依頼する外構業者・ホームセンターやハウスメーカーに、確認申請の対応もしてくれるのか確認しましょう。
これらの業者が引き受けてくれない場合は、お近くの建築士事務所に依頼しましょう。
確認申請の流れ

- 図面作成
- 申請書類作成(法規チェック)
- 確認申請を審査機関に提出・審査
- 確認済証
- 着工
建築基準法上、確認済証が下りた後でなければ、工事を始めることができません。
まとめ
カーポートを作るとき、確認申請をしないと違法になってしまうケースが多いです。
まずは、カーポート設置を依頼する外構業者・ホームセンターやハウスメーカーに、確認申請の対応もしてくれるのか確認しましょう。
これらの業者が引き受けてくれない場合は、お近くの建築士事務所に依頼しましょう。
カーポートの設置は、外構工事に分類されることが多いです。カーポートを作りたいと考えている方は、一括見積サイトの利用がおすすめです。
一括見積サイトを利用することで、簡単に複数の業者から見積もりを取り寄せ、適正な価格を知ることができます。
こちらの記事で、有名な外構工事一括見積サイト6社を比較しています。


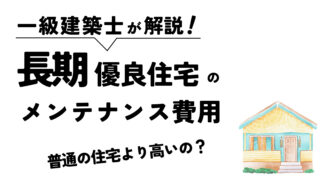




コメント