
住宅性能評価って何?

住宅性能評価と長期優良住宅の違いは?

どっちを取るべき?
こんな悩みを解決します。
- 長期優良住宅はメンテナンスしやすくて長持ちする住宅。
- 住宅性能評価は、住宅の成績表みたいなもの。
- 住宅性能評価で好成績の住宅が、長期優良住宅の認定を受けられる。
- 長期優良住宅が向いている人、住宅性能評価が向いている人が分かります。

建築関係の企業で4年以上働いていて、一級建築士の資格も持っている私、だん(壇)が説明します。
長期優良住宅とよく比較されるのが、ZEHや低炭素住宅などの省エネ住宅です。ZEHや低炭素住宅について知りたい人はこちら
マイホームを検討している人は、住宅展示場へ行く前に資料請求から始めることで、効率的に業者選びができます。また、建てた後で「こんな風にしておけばよかった」といった後悔が減ります。
資料請求を効率よく行うには、タウンライフ家づくりを利用するのがおすすめです。
- 複数社の見積もり
- カタログ
- ラフな間取りプラン
がもらえます。
カタログを見たうえで、行く展示場を選べるので効率的です。
タウンライフは注文住宅部門のアンケート調査で利用者満足度No.1・知人に勧めたいサイトNo.1・使いやすさNo.1の3冠を達成しています。
【PR】タウンライフ
タウンライフ家づくりについての詳細記事はこちら↓
詳細:【長期優良住宅の業者選びにも】タウンライフ家づくり|無料で見積もり+間取り作成
住宅性能評価とは?長期優良住宅との違いも解説

住宅性能評価は、住宅の成績表みたいなものです。

例えば、地震への強さを表す耐震等級は3段階あって、「3」が一番性能が高いです。

学校の成績表と同じですね。
「数学は5段階評価中の3!」みたいな
家の性能って、専門じゃない人にはわかりにくいですよね。
住宅性能評価がない時代は、例えばハウスメーカーから「地震に強い家です。」と言われても、本当かどうか確かめるすべがありませんでした。
でも、住宅性能評価を受けた住宅は、家の性能が数字で分かりるので、希望する性能を持った住宅を作りやすくなります。

住宅の性能を「見える化」。それが住宅性能評価です。
また、国の登録を受けた第三者機関が評価をします。そのため、ハウスメーカーに忖度して等級を偽ったりすることがありません。
住宅性能評価には、設計住宅性能評価と、建設住宅性能評価の2種類があります。
- 設計住宅性能評価:工事が始まる前に図面の審査を受ける。
- 建設住宅性能評価:設計住宅性能評価のときの図面の通りに工事されているかどうか現場検査を受ける。

図面の審査だけだと施工ミスが心配...
という人は建設住宅性能評価を受ければ現場検査を受けられます。
詳細(外部リンク):(一社)住宅性能評価・表示協会HP「パンフレット 住宅性能表示制度」
それに対して、長期優良住宅は、メンテナンスしやすくて長持ちする住宅です。
もう少し正確に言うと、
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の基準に適合しており、特定行政庁(都道府県or市区町村)の認定を受けた住宅を、長期優良住宅と言います。

この「○○等級」が、住宅性能評価の成績です。

このように、住宅性能評価で好成績の住宅が、長期優良住宅の認定を受けられます。
また、建設住宅性能評価では、住宅の工事中や完成後に現場検査を受けますが、長期優良住宅の認定を受けるときには現場検査は受けません。
詳細:【長期優良住宅とは?】認定基準・条件や確認方法を一級建築士が解説
どうやったら住宅性能評価を受けられるの?
住宅性能評価を受けるには、家を建てるメーカーや工務店の人に、「住宅性能評価を受けたい」と相談しましょう。
住宅性能評価の項目一覧(10項目)

- 構造の安定に関すること
(耐震性、耐風性など) - 火災時の安全に関すること
(家の燃えにくさ、避難のしやすさなど) - 劣化の軽減に関すること
(雨漏り・結露対策、シロアリ対策、点検のしやすさなど) - 維持管理・更新への配慮に関すること
(配管の点検・修繕工事のしやすさなど) - 温熱環境・エネルギー消費量に関すること
(壁や屋根の断熱性能、設備の省エネ性能など) - 空気環境に関すること
(有害化学物質の対策、換気など) - 光・視環境に関すること
(窓の大きさなど) - 音環境に関すること
(アパート・マンションの防音など) - 高齢者等への配慮に関すること
(バリアフリー) - 防犯に関すること
(不審者が侵入しにくい)
これらの10個の項目の中で、さらに細かい項目に分かれています。
等級の数字が大きいほど性能が良いです。
また、項目によって、「等級が何段階あるか」が違います。

例えば、「1.構造の安定に関すること」の「耐震等級」は、等級3が一番地震に強いです。

「5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること」の「断熱等性能等級」は等級7が一番性能が良いです。
これらの項目の中から、評価する項目を選びます。
住宅性能評価のメリット

- 専門家でなくても住宅の性能が分かる。
- 建設中や完成後に第三者の検査が受けられる。
- トラブルがあったときに格安で弁護士・建築士等に相談できる。
- 地震保険や住宅ローンの割引がある。
専門家でなくても住宅の性能が分かる。
住宅性能評価を受けた住宅は、家の性能が数字で分かりるので、希望する性能を持った住宅を作りやすくなります。
また、国の登録を受けた第三者機関が評価をするため、評点の信頼性が高いです。
建設中や完成後に第三者の検査が受けられる。

建設住宅性能評価を受ければ、建設中や完成後に、国の登録を受けた第三者機関の検査が受けられます。
検査を受けることで、施工者にプレッシャーがかかるので、施工ミスや手抜き工事を未然に防ぐことができます。
トラブルがあったときに格安で弁護士・建築士等に相談できる。
建設住宅性能評価を受けた場合、住宅の施工不良などのトラブルがあった場合に、専門家(弁護士や建築士など)の相談を無料で受けることができます。
また、1万円の負担で、専門家(弁護士や建築士など)がトラブル解決のサポートをしてくれます。

弁護士に相談できるハードルが低いため、住宅メーカーや施工者も、下手に手抜き工事をすることができなくなります。
地震保険や住宅ローンの割引がある。
- 耐震等級3の場合:50%引き
- 耐震等級2の場合:30%引き
- 耐震等級1の場合:10%引き
住宅性能評価の成績が良い場合に、低い金利でローンを組むことができます。
住宅性能評価のデメリット

申請や書類の作成にお金と時間がかかる。
第三者機関に住宅性能評価をしてもらうために、申請料が要ります。
例:ハウスプラス住宅保証㈱の場合↓
- 設計住宅性能評価:44,000円
- 建設住宅性能評価:77,000円
また、住宅性能評価の申請は、ふつうは住宅メーカーや工務店にお任せします。その場合は、申請事務や書類の作成の料金がかかる場合も多いです。
住宅性能評価と長期優良住宅、どっちを取るべき?向いてる人は?両方取るのは?

- 初期コストがかかっても長く使える家が欲しい人
- 品質が担保された家に住みたい人
- 家の資産価値を保ちたい人(売ったり貸したりしやすい)
- 長い目で見てメンテナンスコストを抑えたい人
詳細:【メリット・デメリット】長期優良住宅はどんな人が向いてる?お得?
長期優良住宅のよくある後悔についてはこちら↓
参考:【一級建築士が解説】長期優良住宅のよくある後悔・後悔しないための注意点
- 施工ミスや手抜き工事が心配な人
- 信頼できる第三者から家の性能を見てほしい人
- 性能が良い住宅が欲しいけど、維持保全の義務がある長期優良住宅は抵抗がある人

建設住宅性能評価を取れば、第三者の検査も受けられるし、弁護士や建築士への相談もできるようになるので、手抜き工事の可能性が減ります。

住宅性能評価を取ると、それと一緒に長期優良住宅の技術的審査を安く受けられるので、両方とも取得するのもおすすめです。
まとめ

- 長期優良住宅はメンテナンスしやすくて長持ちする住宅。
- 住宅性能評価は、住宅の成績表みたいなもの。
- 住宅性能評価で好成績の住宅が、長期優良住宅の認定を受けられる。
- 長期優良住宅が向いているのは、初期コストがかかっても長く使える家が欲しい人。
- 住宅性能評価が向いているのは、施工不良や手抜き工事が心配な人。
マイホームを検討している人は、住宅展示場へ行く前に資料請求から始めることで、効率的に業者選びができます。また、建てた後で「こんな風にしておけばよかった」といった後悔が減ります。
資料請求を効率よく行うには、タウンライフ家づくりを利用するのがおすすめです。
- 複数社の見積もり
- カタログ
- ラフな間取りプラン
がもらえます。
カタログを見たうえで、行く展示場を選べるので効率的です。
タウンライフは注文住宅部門のアンケート調査で利用者満足度No.1・知人に勧めたいサイトNo.1・使いやすさNo.1の3冠を達成しています。
【PR】タウンライフ
タウンライフ家づくりについての詳細記事はこちら↓
詳細:【長期優良住宅の業者選びにも】タウンライフ家づくり|無料で見積もり+間取り作成


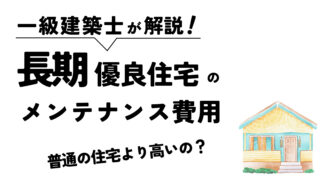




コメント